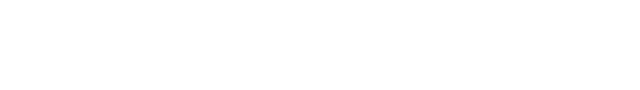保湿剤比較 種類
保湿剤にも種類があるのをご存知ですか?
「保湿剤=ヒルドイド」と思われている方も多いかもしれませんが、実は保湿剤にはいくつかの種類と役割があり、肌質や状態によって使い分けることがとても大切です。
ちなみに、「ヒルドイド」一択というのは日本特有の傾向で、欧米ではセラミドなどバリア機能を補う成分を含む保湿剤の方が推奨されることもあります。
保湿剤の分類:「モイスチャライザー」と「エモリエント」
保湿剤は大きく分けて、以下の2種類があります:
| 分類 | 役割 | 代表例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| モイスチャライザー | 肌に水分を与える | ヘパリン類似物質、尿素、セラミド など | うるおいを「与える」タイプ。乾燥した肌を潤す。 |
| エモリエント | 肌から水分が逃げないようにふたをする | ワセリン、プロペト など | うるおいを「守る」タイプ。外的刺激から肌を守る。 |
例えるなら、乾燥した畑に水をまくのがモイスチャライザー、水が逃げないようビニールハウスをかぶせるのがエモリエント。両方をうまく組み合わせて使うのが理想的です。
💡「保湿しているのに乾燥する…」そんな時は?
ワセリンなどのエモリエントだけではうるおいが足りない場合は、モイスチャライザーで水分を与えることが大切です。
逆にモイスチャライザーを塗ってもすぐ乾いてしまう…という方は、その上からワセリンでふたをすると効果が高まります。
主な保湿成分とその特徴
🔹 ヘパリン類似物質(ヒルドイドなど)
-
-
皮膚に水分を補給し、肌本来のバリア機能をサポート。血行促進・抗炎症・保湿作用。アトピーや乾燥肌など幅広く使用。
-
モイスチャライザーに分類されます。
-
軟膏・クリーム・ローション・泡・スプレーなどさまざまな剤型があります。
-
-
軟膏:保湿力が高く、刺激が少ない(敏感肌・赤ちゃんにおすすめ)
-
クリーム:適度なうるおいで使いやすい
-
ローション:さらっとした使い心地。広範囲に塗りやすい
-
泡/スプレー:べたつかず、子どもにも使いやすい
※油分が少なくなるほど、さっぱりした使用感になります。
🔹 尿素製剤(ウレパール、パスタロンなど)
-
水分保持と角質をやわらかくする作用があります。
-
10~20%の濃度で使用され、特に手足のごわごわ肌やかかと・ひじなどの厚い皮膚、毛孔性苔癬(二の腕や太もものブツブツ)に効果的。
-
刺激を感じやすいこともあるため、顔や敏感な部位には不向きなことも。
🔹 セラミド(市販のスキンケア製品に含まれる)
-
皮膚のバリア機能を担う重要な成分で、加齢や乾燥で減少します。
-
医薬品ではありませんが、敏感肌や乾燥肌の方に推奨される保湿ケアの要です。
-
補うことで肌のうるおいを保ちやすくなります。
(右写真はあくまで例です。特定の製品をおすすめしているわけではありません)
🔹 ワセリン(プロペト、白色ワセリン、サンホワイトなど)
-
肌にふたをすることで水分の蒸発を防ぎ、外部刺激から守ります。刺激が少なく、バリア機能を高める。
-
エモリエントに分類され、赤ちゃんや敏感肌でも使用可能。
-
純度によって種類があり:
-
黄色ワセリン → 白色ワセリン → プロペト → サンホワイトと右にいくほど精製度が高く、刺激が少ない
-
-
花粉症の季節には鼻や目の周りに塗ってバリアを作るのもおすすめ!
-
荒れた口元には、食事前に塗ると刺激を防げて治りが早くなることも。
🔸剤型による違い(ローション・クリーム・軟膏)
-
ローション:広範囲や頭皮に使いやすく、ベタつきが少ない。夏場や軽症時に。
-
クリーム:しっとりなじみ、使い心地がよい。日常的なスキンケアに向いています。
-
軟膏:保湿力・密封力が高く、乾燥や刺激から守ります。冬場やひどい乾燥に。
💡当院の対応
当院では、患者さまの肌の状態・季節・ライフスタイルに応じて、最適な保湿剤を処方しています。市販薬との違いや塗り方についてもご説明しますので、お気軽にご相談ください。