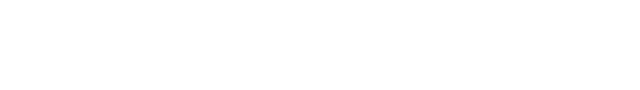アトピー性皮膚炎
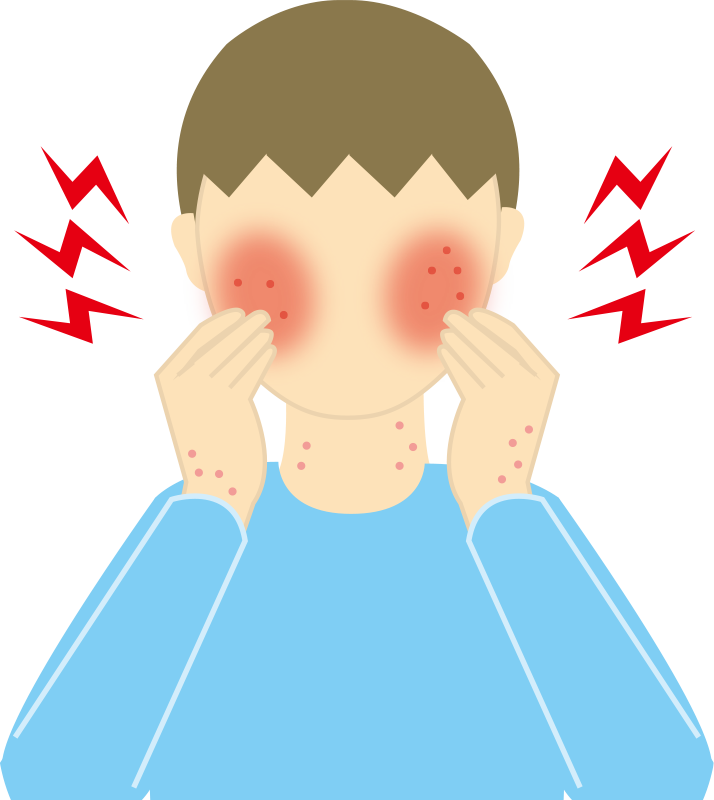 アトピー性皮膚炎とは
アトピー性皮膚炎とは
かゆみのある赤みやぶつぶつ(湿疹)、皮膚炎が慢性的によくなったり悪くなったりを繰り返しながら続く皮膚炎をアトピー性皮膚炎といいます。
乳幼児から小児に多い疾患で、10人に1人がアトピー性皮膚炎だといわれます。小児期にしっかり保湿をしてバリアを高めたり、おこしてしまった皮膚炎を継承の段階ではやめに抑えることができていると、大人になるにつれて皮膚炎が消失~軽度になることが多いです。しかし小児の頃は比較的おさえられていたのに、季節の変わり目やなんらかのアレルギー、ストレスなどが原因で成人になってから症状が悪化する方もいます。
原因
アトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能が弱い「アトピー素因(体質)」を持つ方に、さまざまな刺激やアレルゲン(アレルギーの原因物質)が加わることで、皮膚炎が引き起こされる疾患です。
皮膚には本来、外からの刺激や異物の侵入を防ぐ「バリア機能」が備わっていますが、アトピー体質の方はこのバリア機能が生まれつき弱く、皮膚が乾燥しやすい傾向があります。
このバリアが壊れた皮膚に、アレルゲンや物理的な刺激が加わることで、かゆみや炎症が生じ、湿疹を繰り返すようになります。
🔹 アレルゲンとは?
アレルゲン(アレルギーの原因物質)は人によって異なり、以下のようなものが挙げられます:
-
食物(卵、牛乳、小麦 など)
-
ハウスダスト・ダニ
-
花粉
-
動物の毛やフケ
-
カビ(真菌) など
中でも「カビ」と聞くと驚かれるかもしれませんが、実はヒトの皮膚には「常在菌」として、マラセチアやカンジダといったカビの仲間(真菌)が常に存在しています。これらは普段は悪さをしませんが、汗をかいたままの皮膚や、皮膚が重なり合う部位(関節の内側、下着でこすれる部分、赤ちゃんの首や足のしわなど)では菌が増殖しやすくなります。
このような真菌に対してアレルギーを持っている方は、菌が増えることでかゆみが強まり、かきむしってしまうことでさらに湿疹が悪化する…という悪循環に陥ってしまいます。
🔹 かゆみと湿疹の悪循環
皮膚をかきむしることで、さらにバリア機能が低下し、アレルゲンや外的刺激がより侵入しやすくなります。これがまた新たな炎症やかゆみを引き起こし、「かゆい → かく → さらに悪化する」という悪循環(itch-scratch cycle)に入ってしまうのです。
アトピー性皮膚炎の治療は、こうした悪循環を断ち切ることが大切です。そのためには、皮膚のバリアを守るスキンケア、かゆみや炎症を抑える治療、アレルゲンや刺激物の回避といった、複合的なアプローチが必要となります。
検査
アトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能の低下や、体質的なアレルギー傾向、免疫バランスの乱れなどが複雑に関係して起こる慢性の炎症性皮膚疾患です。診断は主に臨床症状や経過から行われますが、必要に応じて以下のような検査を行うことがあります。
🔹 血液検査
以下の項目を確認し、アトピー性皮膚炎の状態や体内のアレルギー反応、感染の有無などを評価します。
-
総IgE値
アレルギー体質の指標となる抗体です。高値であることが多いですが、正常範囲でもアトピー性皮膚炎がある場合もあります。 -
特異的IgE抗体(アレルゲン検査)
スギ、ダニ、ハウスダスト、食物(卵・牛乳・小麦など)など、特定のアレルギーの原因物質(アレルゲン)に対する感作の有無を調べます。また、アトピー性皮膚炎や喘息などのアレルギー疾患がなく、「何となくアレルギーがあるか気になる」といった目的での検査をご希望される場合には、自費での対応となりますのでご了承ください。 -
好酸球数
アレルギー性疾患で増加する傾向があります。 -
TARC(胸腺・活性化調節ケモカイン)
炎症の程度や病勢の目安になるマーカーで、治療経過の指標としても有用です。 -
LDH(乳酸脱水素酵素)
皮膚の炎症や細胞の傷害を反映することがあります。 -
CRP・白血球数
感染の有無や、体内の炎症状態を評価するために測定します。
🔹 皮膚パッチテスト/プリックテスト(必要時)
-
食物や金属、化学物質などが皮膚症状の原因になっていないかを調べるために行います。慢性的な湿疹や接触皮膚炎が疑われる場合に実施します。当院ではおこなっておりません。
🔹 必要に応じた追加検査
-
亜鉛・鉄・ビタミンDなどの栄養状態
皮膚の修復やバリア機能に関係する栄養素の欠乏が疑われる場合に確認します。特に亜鉛は低くなりやすく、重症の皮膚炎でいくら外用剤を塗っても治らなかったが亜鉛を内服するとかなり改善するという患者さんは多いです。
検査はすべての患者さんに必須ではありませんが、症状の重さ、年齢、経過、ご希望などに応じて、必要な項目を選んでご案内します。小児の方の採血については必要時近隣小児科へお願いすることがございます。
ご不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。
治療
アトピー性皮膚炎の治療は、「皮膚のバリア機能を守るスキンケア」と「炎症を抑える治療」の二本柱で進めていきます。症状の程度や患者さん一人ひとりの生活環境、年齢に合わせて、適切な治療法を選択することが大切です。
🔹 基本となる治療
-
保湿剤(外用)
乾燥を防ぎ、皮膚のバリア機能を整えることで、炎症を起こしにくい肌を保ちます。アトピー性皮膚炎のすべての段階で欠かせない治療です。 -
抗炎症外用薬(ステロイド外用薬、非ステロイド外用薬)
皮膚の炎症やかゆみをおさえるために使用します。症状の強さや部位に応じて、適切な強さの薬剤を使い分けます。 -
その他の外用薬(抗真菌薬、抗菌薬など)
湿疹の悪化に真菌(カビ)や細菌感染が関与している場合、これらを抑える外用薬を併用することもあります。 -
抗アレルギー薬の内服
かゆみを和らげるために内服薬を使用することもあります。
🔹 中等症~重症の方への治療選択肢
近年、アトピー性皮膚炎に対する治療薬は大きく進歩しています。従来の治療ではなかなか良くならなかった中等症~重症の患者さまにも、もちもちつるつるとした肌を目指せる治療が可能になっています。
-
生物学的製剤(注射薬)
- デュピクセント
- イブグリース
- ミチーガ
- アドトラーザ
体内の炎症を引き起こす特定の物質をピンポイントで抑える、最先端の治療薬です。効果が高く、細菌や ウイルスなどに対する免疫力は下げないので長期間使用できる点も特徴です。生物学的製剤は「アトピーとの闘いを根本から変える」可能性のある治療法です。小児ではデュピクセント(生後6ヶ月以上)、イブグリース(12歳以上かつ体重40kg以上)、ミチーガ(6歳以上)、アドトラーザ(15歳以上)に適応があります。
-
JAK阻害薬(内服薬)
- リンヴォック
- オルミエント(2歳~)
-サイバインコ など
細胞内の炎症シグナルをブロックすることで、皮膚炎の改善を促します。小児から大人まで幅広く適応があり、内服薬であるため通院頻度が少なく済む利点もあります。JAK阻害薬を使用する際には、事前に血液検査や感染症チェックなどの安全性確認が必要となるため、近隣の内科や小児科での検査をお願いしています。
当院では、小児から成人まで数百例を超えるアトピー性皮膚炎の診療経験を持つ皮膚科専門医が診療を担当しております。
患者さんの生活背景やご希望に寄り添いながら、安心して治療を続けていただけるようサポートいたします。
「今の治療でなかなかよくならない」「最新の治療に興味がある」「つるつるもちもちになってみたい」など、どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。